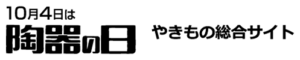日本料理のかたち

日本料理を大きく分けると、本膳料理・会席料理・懐石料理・家庭料理に分けられます。とくに、形式が整い、日本料理の基本となるのが、本膳料理・懐石料理です。
本膳料理とは冠婚葬祭の儀式などに出す正式な日本料理です。本膳には、本汁、なます、煮物、香の物、ご飯を載せ、これに二の膳、三の膳が付き、一汁二菜、一汁三菜、二汁五菜などの献立がたてられます。

会席料理は、略式の宴席料理をさし、料理はおもに汁物、向付(別名さしみ)、口取、鉢肴、煮物、小鉢、茶碗盛りの七品で、さらに品数の多い豪華な料理もあります。

懐石とは、湯石(おんじゃく)で腹を温める程度に空腹を満たす軽い食事という意味で、茶の湯で出す簡単な料理を懐石料理といいます。茶道に作法があるように懐石料理にも作法があります。まず、懐石膳にご飯、汁、向皿が出され、椀盛、焼物、吸物、八寸、湯香の物、菓子と順に出されます。これが今日の家庭料理の基本ともなっています。






向付(むこうづけ)
向付とは懐石の膳の飯・汁椀の向うに付けるところからの呼称で、器と料理のどちらともを表します。向付の器は、とくに決められているわけではなく、一人前ずつ盛り込む小ぶりの器の総称です。中に入れる料理は、刺し身に限らず、浸し物や酢の物など、なにを入れてもかまいません。はじめに登場する晴れがましい器でもあります。
 蓋向(ふたむこう)
蓋向(ふたむこう)
料理におけるもてなしの心得は、なにより夏は涼しげに、冬はあたたかくが身上です。蓋をとったときにほのかに広がる香りと湯気。煮物や蒸し物のあたたかさを逃さないように考えられた蓋付きの器です。
煮もの
椀盛とも呼びます。煮物椀に入れる実だくさんの大きめのお椀をいい、澄まし仕立が多く、葛仕立てもあります。汁ものと思われがちですが、一汁三菜の中の菜にあたります。懐石の中でいちばんのごちそうとされます。
焼もの
焼ものの器に陶磁器を使うようになったのは明治中期以降です。むかしは焼物とはいわずに重引(じゅうびき)とか引菜(ひきな)と呼ばれ、二段重ねの塗箱を用い、上の重に香の物を、下の重に焼きものを盛り付けます。現在では、あらたまった茶事のときのみに使われています。
鉢もの
懐石の基本である一汁三菜の後で、さらに客をもてなしたいという気持ちを表すためにすすめるものが鉢ものです。大鉢にひとつ盛りにし、好きにとって戴くところから預鉢とも呼ばれます。
 八寸
八寸
一期一会の好機を得て、主となり客となった喜びをこめて、亭主と客が盃をかわす場面でだされるのが八寸です。正式には八寸四方の杉のお盆を使います。酒の肴として、海のもの(生臭もの)と山のもの(精進もの)を合わせて出すことが決まりです。客の数よりも多く盛り付けます。