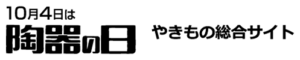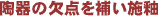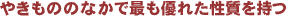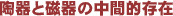やきものの素材

 吸水性のある粘土質の素土に釉薬を施し、磁器よりも低い1100~1200度で焼かれたものです。不透光性で、貫入などの手づくりの良さが出やすく、ぬくもりのある器。素焼きした後、下絵付け、施釉、本焼きで完成します。益子、有馬、笠間、織部、志野、薩摩、唐津、萩焼など、全国のいたるところで焼かれ、それぞれに特徴ある手法で作られています。扱いにはとくに神経質になる必要はありませんが、やわらかい質の器は、洗った後で陰干ししたほうがいいでしょう。磁器に比べ厚みがあり、温かみのある素朴な風合いがあります。
吸水性のある粘土質の素土に釉薬を施し、磁器よりも低い1100~1200度で焼かれたものです。不透光性で、貫入などの手づくりの良さが出やすく、ぬくもりのある器。素焼きした後、下絵付け、施釉、本焼きで完成します。益子、有馬、笠間、織部、志野、薩摩、唐津、萩焼など、全国のいたるところで焼かれ、それぞれに特徴ある手法で作られています。扱いにはとくに神経質になる必要はありませんが、やわらかい質の器は、洗った後で陰干ししたほうがいいでしょう。磁器に比べ厚みがあり、温かみのある素朴な風合いがあります。
 土ものと呼ばれる陶器や土器に対して、こちらは石ものと言われます。原料は、石の粉に粘土や石英などを混ぜた陶石。素土が白く、吸水性がなく、光にかざすと透けるやきもので、1300度前後の高温で焼くため、高度の技術を要するやきものです。また、端正な形に色絵が施され、製作には最も手数がかかります。吸水性がない上釉薬をかけているので、永く使っても汚れや臭いがつきにくく、薄手ですが、陶器より硬くて耐久性もあるため、日常の器として最適です。有田焼、伊万里焼、九谷焼、信楽焼、清水焼、瀬戸焼、美濃焼、砥部焼などがあります。
土ものと呼ばれる陶器や土器に対して、こちらは石ものと言われます。原料は、石の粉に粘土や石英などを混ぜた陶石。素土が白く、吸水性がなく、光にかざすと透けるやきもので、1300度前後の高温で焼くため、高度の技術を要するやきものです。また、端正な形に色絵が施され、製作には最も手数がかかります。吸水性がない上釉薬をかけているので、永く使っても汚れや臭いがつきにくく、薄手ですが、陶器より硬くて耐久性もあるため、日常の器として最適です。有田焼、伊万里焼、九谷焼、信楽焼、清水焼、瀬戸焼、美濃焼、砥部焼などがあります。
 吸水性のない素土に釉薬のかかっていない(ごくまれにかける場合もある)、焼きしめと呼ばれるやきものです。炻器の『炻』とは、実際には漢字辞典になかった文字で、明治40年頃の造語、ストーンウェアという英語の当て字。石のように硬いやきもの、という意味です。アルカリや鉄などの高温で、長時間かけて焼かれます。吸水性がない素土ということが陶器と異なります。備前焼、常滑焼、信楽焼、萬古焼、伊賀焼などがあり、その地方ならではの土の持ち味をいかし、独自の焼き方を開発しています。
吸水性のない素土に釉薬のかかっていない(ごくまれにかける場合もある)、焼きしめと呼ばれるやきものです。炻器の『炻』とは、実際には漢字辞典になかった文字で、明治40年頃の造語、ストーンウェアという英語の当て字。石のように硬いやきもの、という意味です。アルカリや鉄などの高温で、長時間かけて焼かれます。吸水性がない素土ということが陶器と異なります。備前焼、常滑焼、信楽焼、萬古焼、伊賀焼などがあり、その地方ならではの土の持ち味をいかし、独自の焼き方を開発しています。
粘土を原料として、無釉、素焼きで700~800度の低温で焼成されたものです。もろくて水漏れするため食器に向きませんが、植木鉢や焙烙として使われています。最も原始的なやきもので、歴史が古く、日本でも1万年以上前の縄文土器が始まりと言われ、4つのやきものの中では、一番単純な製作過程で作られています。それまで、貝殻や竹筒などの自然の器を利用していた人間たち。粘土を使って、人工の器を形作って焼くということは、人類が科学に目覚めた第一歩と言えるかもしれません。こうして土器は、煮炊き用品からいろいろな用途を持つものへと急速に展開していきます。