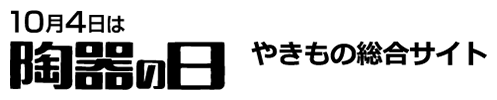彼岸を過ぎ、風の中に少しずつ秋の気配が忍び寄ってくると、月を思い起こさせる器や菓子に手が伸びる。秋の3か月を孟・仲・季と分けた真中が陰暦8月、別名「仲秋」に当たり、さらにその月の満月、すなわち十五夜に出る月こそ名月、というわけだ。前日14日の夜を「待宵」そして16日から20日まで順に「十六夜」、「立待月」「居待月」「臥待月」「更待月」と、月の出る時刻にこと寄せて美称を与えた日本人の、月への思いの深さは格別のものがある。

菓子=玉衣(小蔵亀寿堂)
写真:津留崎徹花 撮影協力:加島美術
雨ではなく、「雲間の月」程度に影の射す銀彩の鉢に盛ったのは、おわら風の盆で有名な、越中八尾の銘菓。泡立てた卵白に寒天と砂糖を加え、表面に黄身を塗って焼き上げた、小蔵亀寿堂の「玉衣」(たまごろも)である。卵焼きを思わせる、こんがりと香ばしそうな黄金色にまず目が引き寄せられ、泡雪のようにはかなく口の中で溶けてしまう食感は、甘さを重く感じさせない。決して高価ではない「おやつ」の菓子だが、ざんぐりと鉢に盛った姿は、雲の切れ間から漏れる光を思わせはしないだろうか。月見といえば団子が定番だが、直接的に月にちなんだ、あるいは月を意匠とした菓子でなくても、器次第で月見の趣向が生まれる。これも器と菓子を組合せるからこその、楽しみのひとつだろう。